
みなさんこんにちは!ソングメーカー代表兼制作者、中小企業診断士の井村淳也です。
経営者の方とお会いするたびに思うこと。
企業文化とは、言葉にするのは簡単ですし、実際よく耳にするものでもあります。
またそれが自社に定着していると考えている経営者の方も、私が現場に入っての肌感覚では決して少なくないと感じます。
――これは診断士として多くの現場で痛感することです。
こちらは私が中小企業診断士として代表を務める、ソング中小企業診断士事務所のホームページです。

あなたの会社には、どんな文化がありますか?
そう問われたとき、多くの経営者や管理職は
「風通しがいい」「挑戦を大切にしている」「人を大事にしている」
といった言葉で答えます。
しかし、その文化が 日々の現場で本当に“行動として再現されているか” と聞かれると、少し言葉に詰まるケースも少なくありません。
組織文化は、理念やスローガンを掲げた瞬間に生まれるものではありません。
また、研修や一時的なキャンペーンで定着するものでもありません。
文化の正体は、もっと地味で、もっと現実的です。
それは、
日々、何が選ばれ、何が見過ごされ、何が繰り返されているか
その積み重ねにほかなりません。
つまり文化とは、
「大切だと言っていること」ではなく、
実際に“繰り返されている行動”の総体なのです。
本記事では、中小企業診断士として数多くの現場を見てきた視点から、
- なぜ文化は意図せず生まれてしまうのか
- 行動が文化に変わるメカニズム
- 文化を壊す要因と、逆に定着させる設計
を構造的に解き明かします。
そして後半では、
行動のリズムと感情を支える「音楽」という情緒インフラが、
なぜ文化づくりにおいて強力な役割を果たすのかについても触れていきます。
文化を「雰囲気」や「気合い」で語るのをやめ、
設計できるものとして捉え直したい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
この記事を読むことで得られること
- 人事評価が「裁定」や「管理」に見えてしまう“構造的な理由”が整理できます
- 共通の価値観がないまま評価すると起きる歪み(ズレ・不信・個人戦)を言語化できます
- 価値観を「共有」から「体感」に変え、評価を納得と成長につなぐ具体的な設計視点が得られます
まず結論:評価制度は“価値観の翻訳装置”なので、先に共通価値観と空気(情緒)を整えない限り、評価は納得ではなく裁定として受け取られます。
なぜ人事評価は“うまく機能しない”のか
多くの企業が、人事評価制度の見直しに取り組んでいます。
評価項目を細かくし、基準を明文化し、面談の頻度を増やす。
それでもなお、現場からはこんな声が聞こえてきます。
- 「結局、何を評価されているのかわからない」
- 「評価が納得できない」
- 「評価面談が苦痛だ」
- 「頑張っても報われない気がする」
制度は整っている。形式的には“正しそう”に見える。
それでも不満が消えないのは、評価制度そのものが悪いからではありません。
評価が担っている役割の設計が、組織の実態とズレていることが原因です。
評価制度を整えても不満が消えない理由
人事評価がうまく機能しない組織には、共通する構造があります。
それは、評価がいつの間にか「人を育てる仕組み」ではなく「人を裁く仕組み」になってしまっていることです。
本来、評価は次のような役割を持つはずでした。
- 何を大切にしている組織なのかを伝える
- どんな行動が歓迎されるのかを示す
- 成長の方向性をすり合わせる
しかし現実には、評価はこう受け取られがちです。
- 点数をつけられる
- 比較される
- 序列を決められる
- 報酬を決める材料にされる
評価の目的が「対話」から「判定」へすり替わった瞬間、
制度はどれだけ精緻でも、現場の納得感は急激に下がります。
評価制度が機能しない最大の理由は、
評価が“未来の話”ではなく“過去の裁定”に見えてしまうことにあります。
評価が「管理」や「裁定」に見えてしまう構造
評価が管理や裁定に見えてしまう背景には、組織側の事情もあります。
- 人件費をコントロールしなければならない
- 昇給・昇格に線を引かなければならない
- 公平性を担保しなければならない
これらは経営として当然の要請です。
しかし、この要請を前面に出しすぎると、評価は一気に“管理装置”になります。
評価面談が、
- 上司が話す時間の方が長い
- 結果の説明が中心
- 数字や基準の話ばかり
- 「どう感じたか」「どうしたいか」が扱われない
こうした場になっていると、部下にとって評価は「聞かされるもの」になります。
この時点で、評価はすでに育成の機能を失っています。
人は「管理されている」と感じた瞬間、防衛的になります。
本音は出ず、無難な言葉だけが残ります。
評価制度が人を分断してしまう瞬間
もう一つ見逃せないのが、評価が組織内の分断を生む構造です。
評価が強く意識されると、人は次のように行動します。
- 失敗を避ける
- 目立つ仕事だけを選ぶ
- 他者と情報を共有しなくなる
- チームより個人最適を優先する
評価が「比較」や「順位」を強く意識させる設計になっているほど、
組織は協力よりも自己防衛に傾きます。
特に問題なのは、
評価されやすい行動と、組織に本当に必要な行動がズレている場合です。
- 地味だが重要な仕事
- 他人を支える行動
- 失敗を拾い上げる行為
- 空気を整える役割
これらが評価に反映されにくい組織では、
誰もその役割を担わなくなります。
結果として、
「評価制度はあるのに、組織が弱くなる」という逆説的な状況が生まれます。
問題は制度ではなく、“評価の意味づけ”
ここまで見てきたように、
人事評価がうまく機能しない原因は、制度の細かさや項目数ではありません。
本質的な問題は、
評価が「何のためにあるのか」が、現場に共有されていないことです。
評価が、
- 成長のための対話なのか
- 組織文化を伝える手段なのか
- 行動の方向性を揃える装置なのか
この意味づけが曖昧なまま運用されると、
評価は必ず「管理」「裁定」「分断」として受け取られます。
次のセクションでは、
評価が「機能する組織」と「機能しない組織」を分ける決定的な違いを、
もう一段深い構造から解き明かします。
評価の前提にあるべきもの──共通の価値観という土台
人事評価がうまく機能しない組織には、ある共通点があります。
それは、評価項目や制度設計以前に、「何を良しとする組織なのか」が十分に共有されていないことです。
評価とは、本来「人を選別する仕組み」ではありません。
組織として大切にしたい行動や姿勢を示し、
「この方向で合っている」と伝えるためのメッセージ装置です。
にもかかわらず、その土台となる価値観が共有されていないまま評価を行うと、
評価は一気に「裁定」や「管理」に見えてしまいます。
評価は「基準」が共有されて初めて納得される
人が評価に納得できるかどうかは、
点数の高さや昇給額だけで決まるわけではありません。
むしろ重要なのは、
- なぜこの評価なのか
- 何を評価しているのか
- 自分はどこを期待されているのか
が理解できるかどうかです。
ここで必要になるのが、共通の価値観=判断の物差しです。
たとえば、
- 売上を最優先する組織なのか
- チームワークを重視する組織なのか
- 挑戦を評価するのか、安定運用を評価するのか
これが曖昧なまま評価が行われると、
社員は「評価者の好み」や「その時の空気」で決まっているように感じます。
その瞬間、評価は信頼を失います。
数値・成果評価が空回りする組織の共通点
「うちは数字で評価しているから公平だ」
そう考える経営者・管理職は少なくありません。
もちろん、数値評価は重要です。
しかし、数値だけで評価を完結させようとすると、必ず歪みが生まれます。
よくあるのが次のような状態です。
- 数字は達成しているが、周囲への影響が悪い
- 短期成果を優先し、長期的な信頼を損ねている
- チームへの貢献が見えなくなる
- 本来大切にしたい行動が評価されない
これは、「成果の背景にある行動や姿勢」を評価の土台に置けていないことが原因です。
数値は結果であって、文化や価値観を直接表すものではありません。
評価が成果主義に偏りすぎると、
組織が大切にしてきた暗黙の価値が、少しずつ壊れていきます。
「何を良しとするか」が曖昧なまま評価する危険性
評価の場面で最も危険なのは、
「評価基準はあるが、価値観が言語化されていない」状態です。
この状態では、
- 評価者ごとに解釈がブレる
- 部署ごとに評価の空気が違う
- 「あの人は評価されているのに、なぜ自分は…」という不信感が生まれる
結果として、評価制度そのものではなく、人間関係が壊れ始めます。
中小企業診断士として現場に入ると、
評価への不満が表に出ている組織ほど、
実は「制度」ではなく「価値観共有」に課題があるケースが大半です。
評価とは、
「この組織は、どんな行動を歓迎するのか」を繰り返し伝える行為。
つまり、評価の前提には必ず共通の価値観が必要なのです。
評価制度は“価値観の翻訳装置”である
評価制度を機能させたいのであれば、先にやるべきことは明確です。
- 組織として、何を大切にしたいのか
- どんな行動が「この会社らしい」のか
- 成果以前に、どんな姿勢を評価したいのか
これらを、言葉と具体行動の両方で共有すること。
評価制度は、価値観を数値や言葉に翻訳する装置であり、
価値観そのものを代替するものではありません。
土台が揃ってはじめて、評価は「納得」と「成長」を生む仕組みに変わります。
共通価値観がないまま評価すると起きる3つの歪み
評価制度がうまく機能しない組織を見ていくと、
制度設計そのものよりも、その前提にある「価値観の不在」が問題になっているケースがほとんどです。
評価は本来、「何を大切にしている組織なのか」を前提に行われるものです。
しかし、その前提が共有されていないまま評価が行われると、
組織の中には静かに、しかし確実に歪みが生まれていきます。
① 頑張りどころが人によってズレる
共通の価値観がない組織では、
「何を頑張れば評価されるのか」が人によって違います。
- ある人は数字を伸ばすことに全力を注ぐ
- ある人は現場の調整やフォローに力を尽くす
- ある人はトラブル対応や裏方業務を引き受ける
どれも組織にとって必要な行動です。
しかし、「何を良しとするか」が共有されていないと、
本人が頑張っているつもりの行動が、評価に結びつかないという事態が起きます。
すると、
- 「結局、何をすればいいのかわからない」
- 「自分の努力は見てもらえていない」
という感覚が広がり、行動の方向性は次第にバラバラになっていきます。
評価制度があるにもかかわらず、組織のベクトルが揃わないのは、この構造によるものです。
② 評価が“好き嫌い”に見えてしまう
共通価値観が言語化・共有されていない状態では、
評価はどうしても属人的に見えてしまいます。
- あの人は評価されている
- でも、なぜ評価されているのかが説明されない
- 基準が見えないから、納得できない
この状態が続くと、評価は次第に
「成果」ではなく「人」に向けられたものだと受け取られます。
本人にその意図がなくても、
評価する側の言葉が足りなかったり、
価値観の前提が共有されていなかったりすると、
評価は簡単に「好き嫌い」や「えこひいき」と解釈されてしまうのです。
これは、評価者の人格の問題ではありません。
評価の“土台”が見えていないことが原因です。
評価が信頼を失うと、
制度そのものへの不信感が組織全体に広がっていきます。
③ チームではなく「個人戦」になる
共通価値観がないまま評価を行うと、
人は「自分が評価されること」だけに意識を向け始めます。
- チームへの貢献よりも、目に見える成果を優先する
- 協力よりも、自分の実績を守る行動が増える
- 情報共有やフォローが減っていく
これは自然な反応です。
評価基準が曖昧な中では、
人は「確実に点が取れそうな行動」だけを選ぶようになります。
結果として、組織は次第に「個人戦」へと傾いていきます。
チームワークや相互支援が評価されないなら、
それらは後回しにされてしまうからです。
本来、評価制度は
「組織として望ましい行動を増やすための装置」です。
しかし、価値観が共有されていない状態では、
評価はむしろ組織の分断を促す装置になってしまいます。
評価の歪みは、人の問題ではなく構造の問題
ここまで見てきた3つの歪みは、
いずれも「社員の意識が低いから」起きているわけではありません。
- 頑張りどころがズレる
- 評価が不透明に見える
- 個人戦になる
これらはすべて、
「何を大切にする組織なのか」が共有されていないまま評価をしているという構造から生まれています。
だからこそ、評価制度を改善したいのであれば、
先に手をつけるべきなのは制度の細部ではなく、価値観の共有です。
次のセクションでは、
ではその共通価値観を、どうやって組織の中に根づかせるのか──
そのための具体的な考え方に進んでいきます。
価値観を“共有”から“体感”へ──評価が機能し始める設計
多くの企業で、人事評価がうまく機能しない理由ははっきりしています。
それは、「価値観を共有している“つもり”」で評価を始めてしまうからです。
評価制度の中には、
「挑戦」「主体性」「チームワーク」「顧客志向」
といった言葉が並びます。
しかし、これらの言葉が現場でどのような行動を指しているのかが体感されていないままでは、
評価はどうしても空回りします。
なぜ「言葉で示す」だけでは足りないのか
価値観は、文章で読んだ瞬間に理解できるものではありません。
人は、価値観を「説明」ではなく「経験」から学びます。
たとえば、
- どんな行動が評価され、
- どんな判断が歓迎され、
- どんな姿勢が「この会社らしい」とされるのか
それを実際の場面で目にし、体験し、繰り返し確認することで、初めて腹落ちします。
逆に言えば、評価基準が文章として存在していても、
- 会議では違う行動が称賛されている
- 忙しいときには価値観が無視される
- 上司自身がその価値観に沿った行動をしていない
こうしたズレがあれば、社員は「結局、何が正解なのかわからない」と感じます。
その瞬間、評価は“制度”から“恣意”に見え始めます。
価値観は「行動・判断・会話」に埋め込む
評価が機能し始める組織には、共通する特徴があります。
それは、価値観が評価シートの中ではなく、日常の行動に埋め込まれていることです。
たとえば、
- 会議で意見が割れたとき
→「この判断は、うちの価値観に照らすとどうだろう?」と自然に問いが出る - 部下の行動を振り返るとき
→結果だけでなく「どんな判断軸で動いたか」が語られる - トラブルが起きたとき
→責任追及より先に「価値観に沿っていたか」が確認される
こうした場面が積み重なることで、
価値観は“守るべきルール”ではなく、“考えるための軸”になります。
この状態になって初めて、評価は「点数付け」ではなく、
価値観を確認し合う対話に変わります。
OJT・会議・日常判断と評価をつなぐ
評価を機能させる最大のポイントは、
評価の場を、評価シーズンだけに閉じないことです。
評価が年に1〜2回だけ語られる組織では、
価値観はどうしても「後付けの理由」になってしまいます。
一方で、評価が機能している組織では、
- OJTの中で
→「今の対応、うちの価値観で言うとどこが良かったと思う?」 - 日常の会話の中で
→「その判断、まさに大事にしている考え方だね」 - 会議の振り返りで
→「今日の進め方、価値観に沿っていた点とズレた点はどこだろう?」
といったやり取りが自然に行われています。
つまり、評価とは
結果を裁定する行為ではなく、価値観をすり合わせ続けるプロセスなのです。
このプロセスが日常に組み込まれている組織では、
評価の場で大きな不満が噴き出すことはありません。
なぜなら、評価の内容はすでに日々の対話の中で共有されているからです。
音楽は価値観共有を加速させる──評価を“納得”に変える装置
人事評価がうまく機能しない最大の理由は、「制度が未完成だから」ではありません。
多くの場合、評価は論理としては正しく、感情としては受け取れない状態にあります。
評価結果を説明され、数値や理由も示されている。
それでも、どこか腑に落ちない。納得できず、モヤモヤが残る。
このズレを生んでいるのは、評価そのものではなく、
その評価が置かれている“空気”です。
評価は、論理よりも「感情」で受け取られる
人は評価を、頭だけで処理しているわけではありません。
- 自分はこの組織でどう扱われているのか
- この会社は、何を大切にしているのか
- この評価は、自分の存在をどう位置づけているのか
こうした問いが、無意識のうちに立ち上がります。
つまり評価とは、
「点数をつける行為」ではなく、「関係性を再確認する行為」なのです。
だからこそ、
共通の価値観が“感覚として共有されていない組織”では、
どれだけ評価基準を整えても、評価は裁定や管理として受け取られてしまいます。
音楽は「この会社らしさ」を一瞬で思い出させる
ここで音楽が果たす役割は、非常にシンプルです。
音楽は、
「この会社は、どんな価値観の場所だったか」を、説明抜きで思い出させます。
文章を読まなくても、
説明を受けなくても、
音を聞いた瞬間に、その場の空気が立ち上がる。
- 挑戦を良しとする会社なのか
- 丁寧さを大切にする会社なのか
- 人とのつながりを重んじる会社なのか
音楽は、こうした価値観を
“理解”ではなく“感覚”として呼び戻す装置です。
評価の場面でこの感覚が共有されているかどうかで、
同じ言葉、同じ評価結果でも、受け取られ方は大きく変わります。
社歌・PRソングは「評価制度の空気」を支える
社歌やPRソングというと、評価制度とは無関係に見えるかもしれません。
しかし実務の現場で見ると、
評価が納得として受け取られる組織には、必ず一貫した“情緒の土台”があります。
- 日常的に触れている音
- 節目で流れる曲
- 集合時に共有されるメロディ
こうした音の積み重ねが、
「この会社は、こういう価値観の場所だ」という前提を、
無意識レベルで共有させています。
その前提があるからこそ、評価は「ジャッジ」ではなく、
「同じ価値観に照らしたフィードバック」として受け取られる。
評価制度を支えているのは、制度設計だけではありません。
その制度が置かれている空気・温度・情緒こそが、
評価を“納得”に変える最後の決定打になります。
評価を機能させたいなら、空気から設計する
診断士として現場に入る中で強く感じるのは、
「評価制度がうまくいかない会社ほど、制度を直そうとする」ということです。
しかし本当に見直すべきなのは、
評価が行われる前後の空気です。
- どんな価値観が日常で感じられているか
- その価値観が、感情として共有されているか
- 評価の言葉が、どんな空気の中で届けられているか
音楽は、この“見えない前提”を整える、最も副作用の少ない方法のひとつです。
評価を変えたいなら、
まず「この会社らしさが、ちゃんと感じられているか」を問い直す。
その土台が整ったとき、
評価は初めて 人を動かす言葉になります。
まとめ|評価制度は“後工程”──先に文化を整える
評価制度がうまく機能しないとき、
多くの組織は「制度が悪い」「基準が曖昧だ」「評価者のスキル不足だ」と考えがちです。
しかし、ここまで見てきたように、問題の本質はそこではありません。
評価が納得されない最大の理由は、
評価の前提となる“共通の価値観”が、組織の中で生きていないことにあります。
何を良い行動とするのか。
どんな判断を、この会社らしいと感じるのか。
成果だけでなく、どんな姿勢やプロセスを大切にしたいのか。
これらが日常の会話・判断・行動として共有されていない状態で評価を行えば、
どんな制度であっても「裁定」「管理」「好き嫌い」に見えてしまいます。
評価は、人を育てる装置ではなく、人を分断する装置になってしまう。
本来、評価とは文化の結果です。
文化が整っている組織では、
評価は「驚き」ではなく「確認」になります。
- 「ああ、この評価はこの会社らしい」
- 「確かに、そういう行動を大切にしてきたよね」
そう感じられるとき、評価は初めて育成として機能します。
そのために必要なのは、
評価項目を増やすことでも、制度を複雑にすることでもありません。
先にやるべきなのは、価値観を“体感できる状態”にしておくことです。
日々のOJT、会議での判断、上司の言葉の選び方。
そこに価値観がにじみ出ていれば、
評価は自然と腹落ちします。
そして、その「この会社らしさ」を
最も無理なく、感情レベルで共有できる装置のひとつが音楽です。
音楽は、評価基準を説明するためのものではありません。
評価が行われる“空気”を整えるためのものです。
「この会社は、こういう場所だよね」という感覚を、
言葉よりも早く思い出させてくれる。
強い組織ほど、評価制度そのものよりも、
評価が行われる前の文化設計に時間をかけています。
評価はゴールではありません。
文化づくりの“後工程”です。
評価を変えたいなら、
まずはその土台となる文化から整える。
それが、評価を「管理」から「育成」に変える、唯一の近道です。
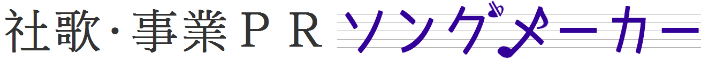


コメント