
みなさんこんにちは!ソングメーカー代表兼制作者、中小企業診断士の井村淳也です。
経営者の方とお会いするたびに思うこと。
顧客対応に多くの時間とコストをかけ、教育も徹底し、アフターフォローも怠っていない。
それなのに、なかなか業績に結び付いていかないことに悩む経営者の方が少なくない。
――これは診断士として多くの現場で痛感することです。
こちらは私が中小企業診断士として代表を務める、ソング中小企業診断士事務所のホームページです。

丁寧に対応した。
時間も手間もかけた。
クレームもなく、満足度も悪くなかった。
それなのに——
数か月後、その会社のことを顧客はほとんど覚えていなかった。
これは珍しい話ではありません。
むしろ、真面目にやっている企業ほど陥りやすい罠です。
多くの企業は、「体験の質」や「サービスの総量」を高めれば、評価や記憶も比例して高まると考えがちです。
しかし、人の記憶はそういう仕組みでは動いていません。
人は、体験のすべてを覚えているわけではない。
覚えているのは、ごく一部の“感情が動いた瞬間”と、“終わり方”だけです。
この人間の特性を説明するのが、ピーク・エンドの法則。
ブランド体験、顧客体験、採用体験、社内イベント——
あらゆる「印象」が、この法則に強く支配されています。
本記事では、
- なぜ「良い体験」が記憶に残らないのか
- ピーク・エンドの法則がブランド評価にどう影響するのか
- そして、それを意図的に設計する方法
を、診断士視点と実務の現場感覚から整理していきます。
選ばれるブランドは、すべてを完璧にやっているのではありません。
“覚えられ方”を設計しているだけなのです。
この記事を読むことで得られること
- 「丁寧にやっているのに思い出されない」現象が起きる理由を、ピーク・エンドの法則で整理できます
- ブランド評価を左右する「ピーク」と「終わり方」を、意図的に設計する考え方が掴めます
- BtoB・無形サービスでも再現できる、感情を動かすポイントと余韻づくりの実務ヒントが得られます
まず結論:ブランドは「全部を完璧にしたか」ではなく、顧客の記憶に残る“ピーク”と“エンド”を設計できたかで評価が決まります。
なぜ「良い体験」なのに記憶に残らないのか
「対応は丁寧でしたよ」
「特に不満はありません」
「悪くなかったと思います」
——これは、一見するとポジティブな評価に聞こえます。
しかし実務の現場では、この言葉の裏に最も危険な兆候が潜んでいます。
それは、“記憶に残っていない”という事実です。
満足度が高くても忘れられるブランドの共通点
記憶に残らないブランドに共通しているのは、「悪くない」ことではありません。
むしろ逆で、全体的に水準が高く、破綻がないという点です。
- 説明はわかりやすい
- 対応は丁寧
- 約束は守る
- トラブルは起きない
どれも正しい。どれも大切です。
しかし、それらが均一に続くだけだと、人の脳は「特筆すべき出来事がなかった体験」として処理します。
結果として、体験は「評価」はされても、「記憶」には残らない。
体験の総量と記憶の関係は比例しない
多くの企業が誤解しているのがここです。
- 「丁寧な対応を積み重ねれば、印象は強くなる」
- 「時間をかければ、価値は伝わる」
実際には、体験の総量と記憶の強さは比例しません。
人は体験を“平均値”では覚えないからです。
長時間の商談も、何度ものフォローも、
記憶の中では一つの塊として圧縮されます。
そのとき脳が参照するのは、
- 一番感情が動いた瞬間(ピーク)
- 終わり方(エンド)
それ以外の大部分は、驚くほど早く忘れられます。
「丁寧だったが印象が薄い」現象の正体
この現象が起きる最大の理由は、
感情の振れ幅が設計されていないことにあります。
- 感動するほど嬉しかった瞬間がない
- 緊張がほどける場面がない
- 「この会社らしい」と感じる象徴がない
体験は“悪くない”が、“動き”がない。
結果、印象が平坦になり、記憶にフックがかからないのです。
診断士視点:BtoB・サービス業で起きがちな勘違い
特にBtoBや無形サービスでは、
「感情に寄せるのは不誠実」「論理が大事」という意識が強くなりがちです。
しかし現場で見てきた限り、
論理が優れている企業ほど、記憶設計が弱い傾向があります。
説明は正しい。提案も合理的。
それでも選ばれないのは、
「何をされたか」より「どう感じたか」が残っていないから。
良い体験が、良い記憶になるとは限らない。
ここを理解しない限り、どれだけ努力しても
「ちゃんとやっているのに、思い出されない会社」
から抜け出せません。
次章では、人が体験をどう記憶するのか——
そのメカニズムそのものを掘り下げていきます。
ピーク・エンドの法則とは何か──記憶を決める心理メカニズム
人は体験を「そのまま」記憶しているわけではありません。
ここに、多くの企業が見落としている決定的な前提があります。
人は体験を“平均”では覚えていない
長い接客、丁寧な説明、何度ものやり取り。
私たちはつい「全体としてどうだったか」で評価されると思いがちです。
しかし実際、人の脳は体験を平均値では保存しません。
体験が終わった瞬間、脳は無意識のうちにこう問い直します。
「結局、この体験は“どうだった”のか?」
この問いに対し、脳が参照するのは体験の全履歴ではなく、
ごく限られたポイントだけです。
ピーク(最高潮)とエンド(終わり方)が記憶を支配する理由
心理学で知られているのが「ピーク・エンドの法則」です。
人は体験を記憶するとき、
- 最も感情が動いた瞬間(ピーク)
- 体験の終わり方(エンド)
この二点を中心に、体験全体を要約します。
途中がどれだけ丁寧でも、
ピークが弱く、エンドが平坦であれば、
体験は「特に印象に残らなかったもの」として処理されます。
逆に、途中に多少の粗があっても、
強いピークと良いエンドがあれば、
人は体験全体をポジティブに記憶します。
脳が体験を要約する仕組み
これは「手抜き」ではありません。
人間の脳が膨大な情報を処理するための、極めて合理的な仕組みです。
すべてを正確に記憶していたら、脳はすぐに限界を迎えます。
だからこそ脳は、体験を象徴的な出来事に圧縮して保存します。
結果として残るのは、
- 「あのとき、どう感じたか」
- 「最後に、どんな気持ちで終わったか」
それ以外の大部分は、意識的に思い出そうとしない限り、消えていきます。
満足度調査が当てにならない理由
ここで、企業活動と強く衝突するのが「満足度調査」です。
アンケートで高得点が出ても、
- 思い出されない
- 指名されない
- 次につながらない
こうした現象が起きるのは珍しくありません。
なぜなら、満足度は「全体評価」を聞いている一方で、
人の記憶は「ピークとエンド」で決まっているからです。
満足している=記憶に残っている、とは限らない。
このズレを理解しないままでは、
どれだけ改善を重ねても「良いが、忘れられる体験」から抜け出せません。
次章では、では具体的に
「どこにピークを設計すべきなのか」
「エンドをどうつくるべきなのか」
その実務的な考え方に踏み込んでいきます。
ブランド体験における「ピーク」の設計
ピーク・エンドの法則を理解したとき、多くの企業が次にこう考えます。
「じゃあ、感動させればいいのか」「サプライズを用意すればいいのか」と。
しかし、ここでピーク設計を誤ると、
“派手だが意味のない演出”になってしまいます。
ピークとは、一番盛り上げることではありません。
感情が最も深く動く一点を、意図的につくることです。
感情が最も動く瞬間をどこにつくるか
ピークは、体験のどこにでも置けるわけではありません。
多くの現場を見てきて感じるのは、感情が動きやすいのは次の瞬間です。
- 「自分のことをわかってもらえた」と感じたとき
- 不安が安心に切り替わったとき
- 努力や背景が言葉にして返ってきたとき
重要なのは、相手の内側で起きている感情の転換点を捉えることです。
ピークは、提供側が盛り上がる瞬間ではなく、
受け手が「意味を見つけた瞬間」に生まれます。
驚き/共感/安心/誇りのつくり方
ピークになりやすい感情には、ある程度の型があります。
- 驚き:想定していなかった理解や視点に触れたとき
- 共感:自分の言葉にならない思いを代弁されたとき
- 安心:不安や迷いを肯定されたとき
- 誇り:自分の選択や立場が肯定されたとき
これらはすべて、「評価」ではなく「関係性」から生まれる感情です。
だからこそ、資料やスペック説明だけではピークは生まれません。
スペックではなく感情がピークになる理由
多くの企業は、
- 「ここが一番すごいポイントです」
- 「この機能が差別化です」
と、ピークを情報でつくろうとします。
しかし、情報は理解されても、感情は動きません。
人の記憶に残るのは、
- 「なるほど」よりも「そうだったのか」
- 「便利」よりも「自分のためだ」と感じた瞬間
スペックは比較されますが、
感情は比較されにくく、記憶に残りやすい。
ここに、ピーク設計の本質があります。
BtoB・無形サービスでのピーク設計例
BtoBや無形サービスでは、
「感動はつくりにくい」と思われがちです。
しかし実際には、ピークは日常的に生まれています。
- ヒアリングで、課題の核心を言語化された瞬間
- 「それを言ってもいいんですね」と安心した瞬間
- 数字や構造が整理され、「道筋が見えた」瞬間
これらは派手ではありませんが、非常に強いピークです。
なぜなら、相手の中で世界の見え方が変わる瞬間だからです。
ピーク設計とは、
何かを足すことではなく、相手の感情が動く一点を逃さずつくること。
次のセクションでは、このピークをどう「終わり方」と結びつけ、
記憶として固定していくのかを見ていきます。
「終わり方」がブランド評価を決める──エンドの重要性
ピークがどれだけ良くても、
終わり方を誤ると、体験全体の印象は簡単に塗り替えられます。
これは感覚論ではなく、ピーク・エンドの法則が示す非常に現実的な人間の認知特性です。
人は体験を「全部」ではなく、最後にどう感じたかで思い出します。
体験の最後が全体評価を塗り替える現象
よくあるのが、こんなケースです。
- 内容は良かったが、最後が事務的だった
- 説明は丁寧だったが、別れ際が慌ただしかった
- 成果は出たが、終わりが突然だった
このとき体験全体は無意識に、
- 「悪くはなかった」
- 「印象が薄い」
という評価に書き換えられます。
逆に言えば、最後さえ丁寧に設計されていれば、体験全体は良く記憶される。
これがエンド設計の恐ろしさであり、強さです。
アフターフォロー・余韻・別れ際の設計
エンドは「終了の瞬間」だけを指しません。
むしろ重要なのは、その前後にある余韻の時間です。
- 最後に何が言葉として残るか
- 別れ際にどんな空気が流れているか
- その後、どんな一言や行動が届くか
ここが雑だと、ピークで生まれた感情は一気に薄れます。
逆に、
- 「ちゃんと見送られた」
- 「大事に扱われた」
という感覚が残ると、体験は“良い記憶”として固定されます。
音楽・言葉・空気がエンドに与える影響
エンド設計で特に強いのが、非言語要素です。
- トーンが落ち着いている
- 言葉が整理されている
- 空気に余白がある
そして、音楽はこのすべてを一瞬で整えます。
静かなBGM、テーマとなる一曲、
あるいは「この場の終わり」を感じさせる音の存在は、
感情を自然にクローズさせ、記憶をまとめる役割を果たします。
人は「終わった」と理解するより先に、「終わった感じ」を受け取っています。
「また会いたい」と思わせる終わり方
エンド設計のゴールは、感動させることではありません。
次につながる余白を残すことです。
- 続きを想像できる
- 関係がここで終わらないと感じる
- また同じ空気を味わいたいと思える
この感覚が残った体験は、比較されにくく、忘れられにくい。
「また会いたい」「またお願いしたい」という評価は、
ピークよりもむしろエンドで決まっていることが多いのです。
次のセクションでは、
このピークとエンドがどのように組み合わさって
「記憶に残るブランド」になるのかを整理していきます。
音楽・演出がピークとエンドを強化する理由
ピークとエンドを設計しようとすると、多くの企業がまず「言葉」や「演出内容」を考えます。
しかし実際に感情と記憶を強く結びつけているのは、言語よりも非言語要素です。
その中でも、音楽が果たす役割は非常に大きい。
音楽が感情と記憶を固定する仕組み
音楽は、意味を理解する前に感情に届きます。
そのため、体験の中で流れた音は「内容」よりも先に記憶に残る。
人は後から体験を思い出すとき、
- あの場の雰囲気
- 空気の温度
- 感情の動き
を、音と一緒に再生しています。
つまり音楽は、体験のピークやエンドを感情ごとパッケージ化する装置なのです。
ブランド体験における“感情のしおり”としての音
音楽は、体験の流れの中で「ここが大事」「ここで終わる」という合図になります。
本でいうなら、感情のしおりのような存在です。
- ここで高揚する
- ここで安心する
- ここで締まる
こうした感情の区切りが音によって明確になると、体験は断片ではなく一本の物語として記憶されます。
逆に音がない体験は、どこがピークでどこが終わりだったのかが曖昧になり、記憶が散ってしまいます。
社歌・PRソング・テーマ音楽の実務的役割
社歌やPRソングは「歌うためのもの」ではありません。
本質的には、感情を呼び戻すためのトリガーです。
- 周年イベントの記憶
- 展示会での体験
- 社内で共有した空気
それらを一瞬で再生させる役割を持っています。
だからこそ、ピークやエンドに音を置くと、体験は時間を超えて使える資産になる。
診断士視点:体験設計に音を入れると失敗しにくい理由
現場で見ていて感じるのは、音楽を組み込んだ体験設計は「ズレにくい」ということです。
言葉や説明は、人によって解釈が分かれます。
しかし音がつくる感情は、比較的そろいやすい。
結果として、
- 印象が安定する
- 評価が極端に割れにくい
- 「なんとなく良かった」が生まれやすい
これはブランド体験において、非常に大きな強みです。
ピークとエンドを本気で設計するなら、
音楽と演出は「装飾」ではなく中核の設計要素として扱う必要があります。
次はいよいよまとめに入り、
「なぜ良い体験ほど設計が必要なのか」を整理していきます。
まとめ|ブランドは「すべての体験」ではなく「記憶」で評価される
企業やブランドが評価されるとき、人は体験の一つひとつを正確に思い出しているわけではありません。
記憶に残っているのは、その体験のピークと終わり方、そしてそこで感じた感情だけです。
だからこそ重要なのは、「どれだけ丁寧にやったか」ではなく、
どこで感情が動き、どんな余韻を残したかです。
ピークとエンドを設計できる企業が選ばれる
選ばれている企業は、偶然評価されているわけではありません。
体験の中に意図的なピークをつくり、終わり方まで設計しています。
- 印象に残る瞬間がある
- 最後に気持ちよく終われる
この2点がそろった体験は、比較の場面で必ず思い出されます。
丁寧さより、印象深さ
丁寧な対応は大切です。
しかし、丁寧さだけでは記憶に残りません。
「悪くなかった」ではなく、
「なんか良かった」「また会いたい」
そう思わせるかどうかが、ブランド評価の分岐点になります。
感情を設計できるブランドが強い
強いブランドは、説明がうまいのではなく、
感情の動線が整っています。
音楽、演出、言葉、空気——それらが組み合わさり、感情と記憶が結びつく。
ブランドとはロゴでもスローガンでもなく、
思い出されたときの感情そのものです。
だからこそ、体験を「全部良くしよう」とするのではなく、
記憶に残す一点をどこにつくるかを考えることが、最も合理的なブランド設計と言えるでしょう。
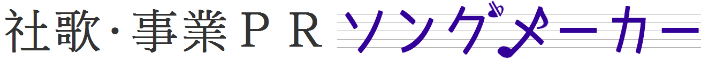


コメント