
音楽を作る。そう聞くと、どこか特別な技術を持った人たちだけの聖域のように感じるかもしれません。
「自分にはセンスがないから」「楽器も弾けないし、楽譜も読めないから」。
そんなふうに、表現することにブレーキをかけてしまう方は少なくありません。
しかし、私が日々音楽制作を通じて出会うのは、技術の有無を超えた、もっと純粋で力強い「表現の芽」が育っていくドラマです。
最初は「何も分からないのでお任せします」と仰っていた方が、最後には「ここは私のこだわりなんです」と誇らしげに語るようになる。
そのプロセスには、人が自分自身の声を取り戻していくような、かけがえのない瞬間が詰まっています。
今回は、依頼者という立場から一歩踏み出し、一人の「表現者」として音楽と向き合うようになるまでの道のりについてお話ししたいと思います。
第1章:「お任せします」に込められた、大切な第一歩
制作のご相談をいただく際、最も多く、そして最も誠実なスタートの言葉があります。
「プロの方に、すべてお任せします」
という言葉です。
これは、決して投げやりな態度ではありません。むしろ、これから始まる未知のプロジェクトに対する、真摯な敬意と少しの不安が混じり合った、とても自然な反応です。
初めて曲を作るという大きな挑戦を前にして、何を基準に選べばいいのか、どう伝えれば正解なのかが分からないのは当然のことです。
「間違えたくない」という優しさ
「お任せします」の裏側には、いくつかの繊細な心理が隠れていることがあります。
- 「音楽的な知識がないから、変なことを言ってプロの邪魔をしたくない」
- 「自分のセンスを否定されたら、少し怖い」
- 「プロが作ったほうが、間違いなく『それっぽい』良いものができるはずだ」
これらはすべて、作品を良いものにしたいという「作品への愛」から生まれる感情です。
だから私は、「お任せで大丈夫ですよ」と心からお答えします。
むしろ、最初から無理に「あなたの個性を出してください」と強いることはしません。
なぜなら、安心感が土台にない状態で絞り出された言葉は、どこか借り物のような、表面的なものになりやすいからです。
まずはプロの技術に身を委ね、音楽が出来上がっていく過程を眺める。その「安心して黙っていられる時間」こそが、心の奥にある本当の願いが顔を出すための準備期間になります。
信頼という名のバトン
「お任せします」は、私にとっては「信頼のバトン」を受け取った瞬間です。
「この人なら、自分のぼんやりとしたイメージを形にしてくれるかもしれない」という期待。
その重みをしっかりと受け止め、まずはプロとしての視点から、その方の想いを翻訳した「最初のスケッチ」を描く。
これが、共同作業の第一歩となります。
第2章:心の扉が開く「ピンポイントの感想」
最初のデモ音源をお送りするとき、私はいつも、受取人であるお客様がどんな表情で再生ボタンを押すだろうかと想像します。
おそらく、期待よりも緊張の方が大きいかもしれません。「自分のイメージと全然違ったらどう言おう」「プロが作ったものに、文句なんて言えないな」。
そんな、試験の結果を待つような空気が伝わってくることもあります。
最初は、遠慮がちな感想が返ってくることが多いものです。
「すごいです、プロの仕事ですね」「思っていた以上にちゃんとしていて驚きました」といった、作品を外側から眺めているような、丁寧なご感想です。
「好き」と「違和感」が、自分自身のものさし
ところが、二回、三回とやり取りを重ねるうちに、変化が訪れます。感想の中に、少しずつ「具体的な手触り」が混じり始めるのです。
- 「サビに入る前の、あのキラキラした音がなんだか好きです」
- 「歌詞のこの一言が、今の自分にすごく刺さりました」
- 「ここは素敵なメロディだけど、少しだけ切なすぎる気がして……」
こうした言葉が出てきたとき、私は内心で「扉が開いた!」と歓喜しています。
なぜなら、お客様が音楽を「評価の対象」ではなく、「自分の心と照らし合わせる鏡」として使い始めた証拠だからです。
専門用語である必要は全くありません。「なんとなく好き」「なんとなく違う」。
その「なんとなく」の中にこそ、その方だけの判断基準(アイデンティティ)が眠っています。
理論的な正解よりも、本人の感覚がどう動いたか。それが音楽に命を吹き込む、最も重要なエネルギーになります。
「判断軸」が育つプロセス
この段階に入ると、お客様の行動も変わってきます。
「通勤中に何度もリピートして聴いてみました」「静かな夜に聴いたら、また印象が変わりました」といった報告をいただくようになります。
それは、誰かに言われたからではなく、自分自身の内側から湧き出た「もっとこの曲を知りたい」という好奇心の現れです。
この時、曲との距離は一気に縮まり、他人事だった音楽が「自分の曲」へと変貌を遂げていきます。
第3章:主語が「私」に変わる、転換点の訪れ
制作の中盤に差し掛かると、コミュニケーションの質が劇的に変化する瞬間があります。私が「転換点」と呼んでいるこのフェーズでは、お客様の使う言葉から「遠慮」が消え、代わりに「意志」が宿り始めます。
主語のシフト
初期のやり取りでは、主語が「プロ」や「世間」であることが多いです。
「プロの方はどう思いますか?」「普通はどちらが良いんでしょうか?」
しかし、ある地点を境に、主語は「私」に切り替わります。
- 「私は、こっちのメロディの方が自分らしいと感じます」
- 「私は、この一節をもう少し大切に伝えたいんです」
この変化こそが、依頼者が「クリエイター」へと進化した証です。自分の感性を信じ、それを言葉にする勇気を持てたということ。
この瞬間、私たちの関係は「先生と生徒」や「業者と顧客」ではなく、同じゴールを目指す「チーム」になります。
「こんなこと言ってもいいですか?」の向こう側
時折、「こんなわがままなこと、プロの方に言っていいんでしょうか?」と、申し訳なさそうに質問されることがあります。
私はいつも「もちろんです!」とお答えします。
「言っていいか」を悩むのは、それだけ真剣に曲と向き合っているからです。どうでもいいことなら、悩むことさえありません。
迷いながらでも、言葉を尽くして伝えようとしてくれる。そのプロセスこそが、曲に深みと説得力を与えます。
プロの技術は、その「わがまま(=こだわり)」を実現するためにあるのですから。
第4章:感情を「素材」として扱う技術
制作が進むにつれ、お客様は驚くほど客観的に自分自身を眺めるようになります。これは、プロのアーティストが日々行っている「セルフプロデュース」に近い感覚です。
自分の感情に価値を見出す
最初は、「自分のプライベートな悩みなんて曲にして価値があるのかな」「大した話じゃないんですけど」と、ご自身の感情をどこか過小評価していた方が、だんだんと自分の過去や今の想いを、大切な「曲の材料」として扱い始めます。
- 「あの時の悔しさがあったから、今がある。だからここは、少し力強いドラムにしたい」
- 「この悲しみを無理に明るくせず、そのまま残しておく方が、救われる人がいる気がします」
自分の心の中にある、綺麗とは言えない感情さえも、表現の一部として肯定する。
これは一種の自己受容のプロセスでもあります。自分の人生を肯定し、それを音楽という形に昇華させていく。
その姿は、どんな熟練の音楽家よりも凛としていて、美しいものです。
「表現を調整する」という視点
この頃には、お客様は自然と、音量バランスや音色のニュアンスについても意見をくださるようになります。
「ここは歌を目立たせたい」「ここは伴奏に包まれたい」
それは、知識として音楽を知っているからではなく、自分の感情をどう配置すれば一番心地よいかを、身体感覚で理解しているからです。
最初は「任せます」と言っていた人が、今は「この曲を、当時の自分に届けるならどう響くべきか」を考えている。その視点の広がりは、制作を始める前には想像もできなかった、素晴らしい成長です。
第5章:なぜプロは、あえて「一歩引く」のか
ここで、私の制作スタイルについてもお話しさせてください。私は制作の後半になるほど、意識的に「一歩引く」ようにしています。
それは、手抜きをするためでも、責任を回避するためでもありません。
主役であるお客様が、最後に自分の足でゴールテープを切るためです。
「正解」は私の外側にある
プロの経験があれば、それなりに綺麗で、誰もが納得するような「無難な正解」を提示することは簡単です。
しかし、私が提示する正解が強すぎると、その曲はお客様のものではなく、「プロに作ってもらった、よくできた借り物」になってしまいます。
- プロが前に出すぎると、依頼者は「確認係」になってしまう。
- プロが決断を奪うと、依頼者は「受け身」に戻ってしまう。
それでは、せっかく育ってきた「制作者としての意識」が萎んでしまいます。だから私は、選択肢を提示し、メリットとデメリットを説明しますが、最後の「決断」はできるだけお客様にお返しするようにしています。
伴走者としての役割
私の役割は、真っ暗な道の中にいるお客様の足元を照らす懐中電灯のようなものです。どの道を通るかは、お客様が決めること。
私は、「こっちの道は少し険しいけれど、景色は綺麗ですよ」「あっちの道はスムーズですが、少し普通すぎるかもしれませんね」と、ガイドに徹します。
お客様が自分で選んだ道だからこそ、完成した時に「私が作った」という強い自覚と誇りが生まれます。その自負こそが、曲を完成させた後の人生においても、一歩前に進む勇気を与えてくれると信じているからです。
まとめ:音楽を「作り終えた」後の、新しいあなたへ
制作の旅が終わる頃、出来上がった音源を聴きながら、多くの方がこう仰います。
「なんだか、昔から自分の中にあった曲のような気がします」
最初は「お任せします」という言葉から始まった旅が、いつの間にか、自分自身の深い部分を掘り下げる探求へと変わっていた。迷い、悩み、何度も聴き返し、修正を重ね、自分の言葉で想いを伝えた。そのすべてのプロセスが、曲という形に刻み込まれています。
「もらった曲」ではなく「産んだ曲」
それはもう、どこかのプロが作った「提供品」ではありません。あなたが悩み、決断し、命を吹き込んだ、世界にたった一つの「あなたの曲」です。
うまいかどうか、評価されるかどうか。そんな小さな枠組みを超えて、自分自身の嘘のない響きを形にできたという事実は、何物にも代えがたい宝物になります。
「自分には無理だ」と思っていた場所から、一歩ずつ進んで、気づけば対等な制作者として私と語り合っていた。
その変化を一番近くで見守らせていただけることは、制作者として、そして一人の人間として、これ以上の喜びはありません。
もし今、胸の奥に小さな想いがありながら、「表現する資格がない」と諦めかけている方がいたら、どうか忘れないでください。
音楽は、技術や知識から始まるものではありません。あなたの「伝えたい」「残したい」という微かな願いから始まります。
まずは「お任せ」からでいい。そこからゆっくりと、あなた自身の声を一緒に探していく旅に出ませんか。
その先には、今まで見たことのない、表現者としてのあなたが待っているはずです。
あなたが自分の曲を、自分の手で抱きしめるその日まで、私は最高の伴走者として、隣で歩み続けます。
次は、あなたの物語を聴かせてください。一緒に、新しい音楽を始めましょう。
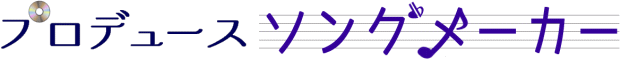

コメント