
みなさんこんにちは!ソングメーカー代表、兼制作者の井村淳也です。
よさこい楽曲を制作していると、「伝統的に」「和風で」といったご要望をいただくことがあります。けれど、その言葉を文字どおりに受け取って“和の音階”をそのまま使ってしまうと、どこか懐かしさを通り越して「少し古い印象」に聴こえてしまうことがあります。伝統を大切にしながらも、現代の感性に響くサウンドを作ることは、言葉にするよりもずっと難しい課題です。
和楽器や民謡に使われる音階には、ヨナ抜き音階、民謡音階、律音階など、いくつもの種類があります。これらをそのまま現代的なリズムやアレンジに当てはめると、メロディが浮いてしまうことがあります。その理由は、「使われる文脈」が変わっているからです。
今の時代に求められているのは、「伝統を感じながらも、都会的で洗練された響き」を持つ音楽です。そのためには、単にスケール(音階)を選ぶだけでなく、「どのように崩すか」「どこを現代的にずらすか」という発想が欠かせません。
本稿では、よさこい・祭り曲の制作を中心に、現場で実際に行っているスケール選択と調整の工夫を紹介します。伝統を尊重しながらも、現代のリスナーに届く“新しい和の響き”を作るためのヒントを、音階の視点からお伝えしていきます。
伝統旋律が古く聴こえる理由と現代的和楽の設計方法
伝統的な日本の旋律を使うと、なぜ「古く」聴こえてしまうのかの説明
伝統的な日本の旋律を使うと、なぜ「古く」聴こえてしまうのでしょうか。
その原因は単純に「古い音階だから」というわけではありません。むしろ、“当時の使われ方”が現代と合っていないことが最大の理由です。
たとえば、ヨナ抜き音階(ドレミソラ)を使うと、どこか懐かしい雰囲気になります。これは明治から昭和にかけての童謡や歌謡曲に多く使われたことで、私たちの耳が「古き良き時代の音」として記憶しているためです。
つまり音そのものではなく、「その音をどのような場面で聴いてきたか」という聴覚的記憶が、“古さ”の印象を決めているのです。
さらに現代のリスナーは、ポップスや映画音楽、アニメソングなど、非常に幅広いサウンド環境で日常的に音を聴いています。そのため、単一のスケールに依存した旋律は単調に感じられやすく、構成の幅が狭く聴こえてしまいます。
特に和楽器を使う場合、「伝統=スケールの制限」と捉えてしまうと、表現の自由度を自ら狭めてしまうことになりかねません。
また、もう一つの理由は「リズムとの相性」です。
伝統音楽では、メロディが主役であり、拍子やリズムは比較的自由に揺れ動いていました。ところが現代のよさこい曲では、BPM120〜140のダンサブルなビートに乗せることが一般的です。
このとき、音階がもつ自然な“間”や“余白”がリズムの強さによって押しつぶされてしまうと、旋律が浮いて聴こえます。逆に、ビートにぴったり合わせようとして音を詰めすぎると、今度は“演歌調”や“懐メロ”の印象が強くなってしまうのです。
ここに、現代的な和の音楽が抱えるジレンマがあります。
伝統のエッセンスを取り入れようとすればするほど、懐かしさが先に立つ。
しかし完全にポップス寄りにすると、“和の魂”が消えてしまう。
このバランスの取り方が、作曲家やアレンジャーにとって最大の挑戦になります。
そして実は、もうひとつ見落とされがちな要素があります。
それは「音色の進化」です。
古い旋律が古く感じられるのは、メロディだけでなく、それを鳴らす音色の側にも理由があります。
尺八や篠笛などの生楽器をそのまま使うと、響きの倍音構造や息づかいが極めてナチュラルで、現代的なデジタルサウンドとの“解像度の差”が生じます。
結果として「ミックス上で浮く」──これも古さを感じさせる一因です。
現代の耳に届く“伝統旋律”を作るためには、この三つの壁を意識する必要があります。
- 聴覚的記憶による印象の壁
- リズム構造との親和性の壁
- 音色バランスの壁
これらをすべて越えるためには、単に伝統を再現するのではなく、「現代のリスナーが心地よく感じる“和”とは何か」を再定義することが求められます。
その鍵を握るのが、「スケールの選び方と崩し方」です。
次のセクションの予告と制作プロセスの導入
次のセクションでは、具体的にどのようなスケール設計によって“古くない伝統旋律”を作り出せるのかを、実際の制作プロセスを交えながら紹介していきます。
伝統旋律をモダンに響かせるためのスケール設計と実践テクニック
モダンに響かせるためのスケール設計の出発点を解説します
伝統旋律を現代的に響かせるには、まず「スケールをどう使うか」を見直すことが出発点になります。ここでのポイントは、“選ぶ”よりも“削る・ずらす・混ぜる”という発想です。
古くから使われてきたヨナ抜き音階や律音階は、それぞれが明確な特徴を持っています。たとえば、ヨナ抜き音階(ドレミソラ)は明るく伸びやかで、日本の歌謡曲に数多く使われてきました。一方で律音階(ドミファソシ)はどこか神秘的で、尺八や笙などに多く登場します。これらの音階は単体では魅力的ですが、現代のトラックメイクやダンスミュージックのリズムにそのまま当てはめると、旋律が浮いてしまうことがあります。
スケール操作の具体手法をそのまま記載します
そこで、私はまず“音を減らす”ところから始めます。
伝統音階のすべてを使わず、要素を絞ってあえて余白を作るのです。
たとえば、ヨナ抜きのうち「ミ」を抜いて四音構成にしたり、あえて半音を入れて緊張感を加えたりします。この“揺らぎ”が、リスナーの耳に「和風だけど新しい」と感じさせるポイントになります。
また、最近では「モード音階」との掛け合わせも有効です。
ドリアンモードやミクソリディアンモードなど、西洋音楽のスケールをベースにしながら、日本的な響きを意図的に織り交ぜることで、懐かしさと都会的な響きの両立が生まれます。
たとえば、ヨナ抜き音階の“ソ”を“ファ”に置き換えるだけで、少し切なさを帯びた現代的な印象に変化します。たった1音の違いで、聴き手の感情は大きく変わるのです。
基音の扱いと安定性についてそのまま記載します
さらに重要なのが「基音(トニック)」の扱い方です。
日本的な旋律では、音の終着点を曖昧にすることで“余韻”を生み出します。
しかし、ビートが強い現代音楽では、曖昧さがリズムの安定を損なうことがあります。そこで私は、ベースラインでトニックをしっかり支えつつ、メロディ側ではあえてトニックに戻らない設計を取ります。これによって、土台は安定しながらも、上モノが流動的に動く──そんな立体的な構造が生まれます。
この「安定と曖昧さの両立」こそが、モダンな“和”を作る上で欠かせない設計思想です。
伝統旋律は、どこか語りかけるような抑揚を持っています。それを現代のサウンドに翻訳するためには、旋律をそのまま写すのではなく、「構造のエッセンス」を取り出す必要があります。つまり、旋律をコピーするのではなく、文法を借りるという考え方です。
スケールの切り替えと楽曲内展開の設計について
もう一つ意識したいのが、スケールの“出会わせ方”です。
イントロでは民謡調の旋律、サビではポップス寄りのメジャースケール──このように楽曲内でスケールを切り替えることで、1曲の中に“旅のような展開”を作ることができます。
これを意図的に設計することで、聴き手は「懐かしいけど新しい」という感覚を自然に受け取るのです。
現場では、これを「和と洋のコード・ハーフミックス」と呼んでいます。
コード進行自体は欧米的に構築しつつ、旋律部分で日本的スケールの要素を“香りづけ”として散りばめる。この構成は、現代のよさこい曲や地域祭り音楽に特に有効です。なぜなら、観客の年齢層が幅広く、世代を越えて親しみを持たせる必要があるからです。
スケール再構築の効果とまとめ
結果として、リスナーの記憶の中にある“和”を呼び起こしつつ、同時に“今っぽいノリ”を感じさせることができる。
この微妙なバランスを支えているのが、スケールの再構築という見えない設計です。
伝統旋律をモダンにするというのは、過去を否定することではありません。
むしろ、伝統を「素材」として再解釈する作業です。
どの音を選び、どの音を抜き、どの音をずらすか──それだけで“和”の印象は何倍にも広がります。
次のセクションでは、実際の制作現場でどのようにスケールを運用し、具体的にどんな“ずらし”を加えているのかを、実践的な事例をもとに紹介していきます。
現場での実践例と音の抜き方でよさこい曲や祭り曲をモダンに響かせる方法
制作現場で直面する耳の違和感と音を抜く重要性の説明
実際の制作現場では、理論だけでは解決できない「耳の違和感」との戦いが続きます。
とくに、よさこい曲や地域の祭り曲のように、“熱量”と“統一感”が求められる現場では、音階の設計以上に「どこまで音を抜くか」が作品の印象を大きく左右します。
和の雰囲気を強めるときの具体的な音の抜き方
たとえば、あるチームから「もっと和の雰囲気を強く」と言われたとき、私が最初に行うのは“音を足す”ことではなく、“引く”ことです。
具体的には、コード進行の中からテンションノートを外し、メロディも半音進行を極力減らします。
これにより、全体の響きに“間”が生まれ、日本語の発音とリズムに自然なゆとりが戻るのです。
結果的に、聴き手は「どこか懐かしい」「でも重くない」という感覚を受け取ります。
若い世代向けのアレンジで使う“ずらす”手法の実践例
逆に、若い世代をターゲットにした曲では、“抜く”のではなく“ずらす”手法を使います。
たとえば、同じヨナ抜き音階でも、3度目の音をわずかに長く伸ばす、または休符を1拍前にずらすだけで、リズムに“グルーヴ”が生まれます。
この“ズレ”こそが現代的な“和”を生み出すエッセンスです。
理論上は同じ音階でも、時間軸の置き方によって印象がまったく変わるのです。
テンポ変更の要望に対する具体的な対応と休符の使い方
ある現場で、振付師の方から「踊りの動きが細かくなったので、もっとテンポを速くしてほしい」と要望を受けたことがありました。
単にBPMを上げると、音の間が詰まり、せっかくの“和の余白”が消えてしまいます。
そのとき私は、旋律の音数を減らし、1フレーズの最後に小節をまたぐような“浮遊する休符”を置きました。
これにより、テンポは速くなっても“心の呼吸”が残る構成になり、振付との一体感が生まれたのです。
音を抜く・ずらす行為の本質と聴き手の呼吸をデザインする考え方
このように、音を抜く・ずらすという行為は、単なるアレンジではなく“聴き手の呼吸をデザインする作業”でもあります。
つまり、旋律の隙間こそが“和の美学”を形づくっているのです。
現場での対話と地域性を反映した音作りの重要性
もうひとつ重要なのは、現場での対話です。
よさこいのチームや演舞団体は、それぞれが大切にしている「地域性」や「想いの軸」を持っています。
たとえば、北海道のチームは広大な自然や厳しい冬を象徴する音を好み、九州のチームは情熱的でリズミカルなリズムパターンを求める傾向があります。
同じ“和の音階”を使っても、求められる“温度”がまったく違うのです。
感覚的な対話で到達するチームらしい和の創出
現場で「この音は冷たい」「もう少し熱を感じるように」といった抽象的な表現が飛び交うのも日常です。
そんなとき、スケールや和音を論理的に説明するよりも、“抜く・ずらす・残す”という感覚的な対話の方がはるかに効果的です。
結果として、「伝統的」ではなく「そのチームらしい和」にたどり着くことができます。
音を抜くことが時代性を決めるという気づきとまとめ
このプロセスを経るうちに、私が気づいたのは──
“和音階をどう使うか”より、“どの部分を空けるか”が、その曲の時代性を決めるということです。
音数の多い楽曲が必ずしも現代的とは限りません。
むしろ、音を削り、空間を生かすことで、リスナーは自由に情景を思い描くことができます。
その“想像の余地”が、現代における“伝統の再解釈”なのだと思います。
最終的な目指すべきゴールと現場で必要な力
最終的に、現場で目指すのは「懐かしさ」でも「新しさ」でもありません。
その両方が自然に同居し、“今の空気”として鳴る瞬間です。
そこに到達するためには、理論や知識だけでなく、現場の息づかいを読み取る力──すなわち“聴く力”が欠かせません。
伝統音楽を現代に響かせるまとめとアレンジ哲学|伝統を守るより響かせる方法
まとめ──伝統は“守る”よりも“響かせる”という考え方の要点
伝統を現代に生かすというのは、決して「古いものを壊すこと」ではありません。
むしろ、時代に合わせて“響かせ方”を変えることで、伝統そのものの生命力を長く保つことだと感じています。
和太鼓の力強さ、尺八の息づかい、篠笛のかすれた響き──それぞれが持つ魅力は、どれも唯一無二です。
しかし、それをそのまま現代のステージやスピーカーで再生すると、リスナーの耳には「遠い音」として届いてしまうことがあります。
だからこそ、私たち制作者は、“音の距離”を現代に近づける翻訳者でなければなりません。
楽器同士の混ざり方を整える具体的なミックスの考え方
たとえば、エレキギターと和太鼓を同じ空間で鳴らす場合、単に音量を整えるだけでは十分ではありません。
和太鼓のアタック感を生かすためにギターの低域をわずかに削り、代わりに中域の倍音を少しだけブーストします。
そうすることで、ふたつの音が“混ざる”のではなく“溶け合う”瞬間が生まれます。
それはまるで、異なる言語を話す者同士が、ゆっくりと共通語を見つけていくような感覚です。
伝統を生かすアレンジは翻訳作業であるという視点
伝統を生かすアレンジというのは、つまり異文化の翻訳作業に近いのです。
言葉を変えても、伝えたい想いは同じです。
音の置き換えや構造の調整は、あくまで“届き方”を変えるための工夫にすぎません。
多様なリスナー環境を想定した音作りの必要性
現代のよさこい曲や地域音楽では、リスナーの層が非常に多様化しています。
子どもからシニアまで、ダンサーも観客も、スマートフォンで音を聴く人もいれば、野外ステージの爆音で浴びる人もいます。
だからこそ、“どんな環境でも心に届く音”を目指す必要があります。
そこに求められるのは、単なる伝統再現ではなく、“伝統の再文脈化”です。
制作姿勢としての「響かせる」ことの優先と柔軟性
私は制作を続ける中で、伝統を守ることよりも、「伝統が響く環境を作ること」のほうが、ずっと重要だと感じています。
それは、音の設計に限らず、制作の進め方やチームとの関わり方にも通じます。
古きものを大切にしながらも、新しい技術や考え方を取り入れる柔軟さ。
それがあるからこそ、伝統は生き続け、次の世代に自然と受け継がれていくのだと思います。
音楽が人の記憶を動かすという結論と伝統の継承
最終的に、音楽とは“人の記憶”を動かすものです。
旋律やリズムがいくら変化しても、そこにある想いが変わらなければ、その音楽は確かに“和”として響き続けます。
和太鼓とエレキギターが同じ空間で共鳴するとき、私たちは時間や文化の境界を越えて、同じリズムで心を動かしている。
その瞬間こそが、伝統が現代に生きるということなのです。
未来の伝統音楽の位置づけと私のアレンジ哲学の結び
これからの時代、“伝統音楽”は特別なジャンルではなく、私たちの日常の中に自然に溶け込んでいくはずです。
制作の現場でも、リスナーの感性でも、和と洋、過去と未来が交わるところにこそ、新しい創造の原点があります。
守るよりも、響かせる。
それが、今を生きる音楽家としての、私のアレンジ哲学です。
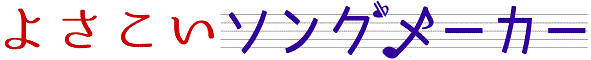


コメント