
AIによる作曲やアレンジが当たり前になりつつある今、「音楽は誰でも作れる時代」に入ったと言われています。ボタン一つでそれらしいメロディが生まれ、迫力のある音源も短時間で完成する──技術的には、確かにそうかもしれません。
では、よさこい曲制作もAIで十分なのでしょうか。
550曲以上のよさこい楽曲を手がけてきた立場から言えば、答えは明確に「違います」。
よさこいの楽曲は、単なるBGMではありません。チームの歴史、今年の覚悟、踊り手の感情、観客との一体感、そして次世代へ引き継がれる“記憶”まで背負っています。そこには、数値化できない感情や、言葉にならない想いが必ず存在します。
この記事では、AIが急速に進化する時代において、よさこい曲制作で人にしかできない役割とは何かを整理します。
AIを否定するのではなく、どう使い、どこを人が担うのか──その境界線を、現場視点で丁寧に紐解いていきます。
この記事を読むことで得られること
- AIでできること/できないことを「賛否」ではなく役割分担として整理できます
- よさこい曲が“機能音楽”ではなく、感情と文脈を背負う芸術である理由が腹落ちします
- AI時代でも人にしか担えない「翻訳」と「総合演出設計」という制作の核心が明確になります
まず結論:AIは制作の強力な補助になりますが、よさこい曲の価値を決めるのは「そのチームで踊る理由」を音にする人の仕事であり、そこは代替されません。
AIで「できること」と「できないこと」を正確に切り分ける
AI時代のよさこい曲制作を語るとき、まず必要なのは「賛成か反対か」という感情論ではありません。
重要なのは、AIで“できること”と“できないこと”を冷静に切り分ける視点です。
ここを誤ると、AIに過度な期待をしたり、逆に本来使えるはずの領域まで拒否してしまったりします。
作曲・アレンジ・音源生成におけるAIの現在地
現在のAIは、
- 一定のジャンル感を持った作曲
- テンポやコード感の整理
- それらしいアレンジや音源の生成
といった「型が明確な音楽制作」を非常に得意としています。
例えば、
「アップテンポで和風テイスト、迫力のある楽曲」
といった条件を与えれば、短時間で“それっぽい音”を出すことは十分可能です。
このスピード感と量産力は、人間には真似できない強みと言えるでしょう。
よさこい制作でAIが得意な領域
よさこい制作の中でも、AIが特に力を発揮するのは以下のような領域です。
- アイデア出しの初期段階
- 仮の方向性確認用デモ
- リズムパターンや構成案のたたき
- 音色のバリエーション探索
つまり、「白紙の状態から選択肢を増やす作業」です。
ゼロから1を生むというより、「0.5くらいまで一気に広げる」のがAIの真価だと言えます。
この工程をうまく使えば、制作スピードは確実に上がります。
AIに任せると“薄くなる”部分
一方で、AIに任せきりにした瞬間、はっきりと薄くなる部分があります。
- チーム固有の背景
- 今年その曲で立つ意味
- 踊り手の感情の揺れ
- 観客との間に生まれる空気
こうした要素です。
AIは「平均的によさそうな音」は作れても、“そのチームでなければ成立しない音”を判断できません。
なぜなら、そこには数値化できない文脈と感情があるからです。
結果として、AI主導の曲は
- 「悪くはないけれど、なぜか心に残らない」
- 「どこかで聴いたことがある気がする」
という印象になりやすい。
これは技術の問題ではなく、役割の問題です。
技術論ではなく「役割分担」の話として捉える
ここで大切なのは、AIを「代替者」として見るのではなく、
制作工程の中の一つの役割として捉えることです。
- AI:選択肢を広げる/可能性を提示する
- 人:意味を与える/文脈を読み取る/決断する
この分担が明確になったとき、AIは脅威ではなく強力なパートナーになります。
よさこい曲制作において最終的に問われるのは、
「音が鳴っているか」ではなく、
「なぜこの音で踊るのかを、チーム全員が腹落ちしているか」です。
AIは提案はできますが、納得を生むことはできません。
その役割を担えるのは、踊り手やチームと向き合い、対話し、迷いながらも一緒に決断できる“人”だけです。
よさこいは“機能音楽”ではない──感情と文脈の芸術
よさこい楽曲をAIで語るとき、どうしても「テンポ」「迫力」「盛り上がり」といった機能面に議論が寄りがちです。
確かに、踊りやすさや構成のわかりやすさは重要です。
しかし、よさこいの音楽は決して“機能音楽”だけでは成立しません。
そこには必ず、感情と文脈が存在します。
よさこい楽曲が背負うもの(物語・歴史・想い)
一曲のよさこい楽曲には、驚くほど多くのものが背負わされています。
チームの成り立ち、地域との関係、過去の挑戦と失敗、今年こそ越えたい壁──
それらが、明示的であれ暗黙的であれ、必ず音の中に織り込まれます。
特に印象的なのは、
- 「この曲で最後にしたい」
- 「この曲で再出発したい」
といった節目です。
そうした場面で求められるのは、単に踊りやすい音ではなく、感情の居場所をつくる音です。
この“背負わせる力”こそが、よさこい楽曲の本質であり、
数値や条件だけでは扱えない領域です。
「踊る人」「観る人」「受け継ぐ人」が同時に存在する特殊性
よさこい音楽の特異性は、三つの立場が同時に成立している点にあります。
- 踊る人:今この瞬間に全力を出し切る存在
- 観る人:初見で感情を受け取る存在
- 受け継ぐ人:数年後、この曲を“記憶”として引き継ぐ存在
この三者は、同じ曲をまったく異なる文脈で受け取ります。
踊り手にとっては“今”の曲であり、
観客にとっては“一瞬の体験”、
後輩にとっては“語り継がれる物語”になる。
この重層的な受け取られ方を前提に設計される音楽は、
そもそも単機能ではありません。
文脈を読む力はなぜAIに難しいのか
AIは、過去のデータから「よくあるパターン」を抽出することは得意です。
しかし、その年、そのチーム、その状況で“なぜこの音なのか”を読む力は持っていません。
たとえば、
- 去年は攻めた。今年はあえて抑える意味
- 強さではなく“静けさ”を選ぶ覚悟
- 技術的には簡単でも、感情的に難しい選択
こうした判断は、データではなく対話の中から立ち上がってきます。
沈黙、言いよどみ、何気ない一言──
そこに含まれる文脈を読み取ることが、よさこい制作では決定的に重要です。
この作業は、現時点では人にしか担えません。
祭り音楽としての本質
よさこいは競技である以前に、祭りです。
祭りの音楽に必要なのは、整った構造や正確さだけではなく、
人の感情を動かし、場の空気を変える力です。
その場に立ち会い、空気を感じ、踊り手や観客の表情を見てきた経験が、
音の設計に反映されます。
AIは音を生成できますが、祭りの“場”を体験することはできません。
だからこそ、よさこい楽曲は今もなお、
人の手と感覚によって磨かれ続けているのです。
人にしかできない①チームの“言語化できない感情”を音に翻訳する力
よさこい曲制作の現場で、最も重要で、最も見えにくい仕事があります。
それは、依頼者自身も言葉にできていない感情をすくい上げ、音に変換することです。
ヒアリングの場で語られる言葉は、実は全体の一部に過ぎません。
本当に曲の方向性を左右するのは、言葉にならない違和感、迷い、覚悟といった「沈黙の側」にあります。
言葉にならない違和感・迷い・覚悟
「何か違う気がするんですけど、うまく説明できなくて……」
この一言は、制作現場で何度も耳にしてきました。
多くの場合、これは“感覚が未整理”なのではありません。
むしろ逆で、感情があまりにもリアルで、まだ言語化できていない状態です。
- 勝ちたい気持ちと、チームらしさを守りたい気持ちの葛藤
- 新しい挑戦への期待と、失敗への恐れ
- 過去を超えたい想いと、否定したくない歴史
こうした相反する感情は、言葉にした瞬間にこぼれ落ちてしまうことがあります。
だから私は、無理に言語化させようとはしません。
まずは、その違和感が「どの瞬間に出たのか」「どこで止まったのか」を一緒に確認します。
ヒアリングで拾われる沈黙・間・温度
AIは言葉を処理しますが、沈黙は処理できません。
しかし、よさこい制作のヒアリングでは、この沈黙こそが最も重要な情報源になります。
- 音源を流した後の数秒の間
- 「うーん」と考え込む時間
- 言いかけて、飲み込んだ一言
これらには、必ず理由があります。
私はヒアリングの場で、相手が言葉を探している時間を遮りません。
沈黙を埋めるよりも、沈黙の温度を感じ取ることを優先します。
この“間”から読み取れるのは、
- 「本当はこうしたい」
- 「でも、それを言っていいかわからない」
という心の揺れです。
この揺れを理解できたとき、音の方向性は一気に定まります。
550曲制作で実感した「最後に効く要素」
550曲以上制作してきて、最後に仕上がりを決定づけるのは、
コードや音色でも、テンポでもありません。
最後に効くのは、“そのチームが音に納得しているかどうか”です。
技術的に完成度が高くても、どこか腹落ちしていない曲は、踊りに現れます。
逆に、多少粗さが残っていても、チームが「これだ」と感じている曲は、驚くほどの迫力を持ちます。
その違いを生むのが、
- 自分たちの想いがちゃんと受け取られているという感覚
- 制作者が“外側”ではなく“内側”に立ってくれているという信頼
です。
この感覚は、AIでは作れません。
なぜなら、それは音そのものではなく、人と人の関係性から生まれる納得だからです。
AIでは代替できない“共感の翻訳”
AIは言葉を音に変換することはできます。
しかし、人が感じている曖昧な感情を、
「こういう音なら伝わるだろう」と想像しながら翻訳することはできません。
共感とは、正解を当てることではなく、一緒に迷い、一緒に決めることです。
よさこい曲制作において人にしかできない仕事とは、
この“迷いを共有するプロセス”そのものだと私は考えています。
だからこそ、AIがどれだけ進化しても、
チームの感情を背負う一曲は、人の手と感覚によってしか生まれません。
それが、550曲制作してきた今、私が最も確信していることです。
人にしかできない②踊り・空間・観客を含めた“総合演出設計”
よさこい曲制作において、「良い音楽」と「強い演舞」を分けて考えることはできません。
なぜなら、よさこいの音楽は踊り・空間・観客の反応まで含めて初めて完成するものだからです。
この“総合演出設計”こそ、AIでは代替できない、人の仕事の核心だと感じています。
演舞・フォーメーション・会場音響との連動
よさこいの楽曲は、スタジオで完結しません。
最終的に鳴るのは、屋外の会場、反響の強いホール、音が遅れて届く広場──
環境は毎年、毎会場で異なります。
そこに加わるのが、
- 大人数フォーメーションの移動
- 隊列が割れる瞬間の視線集中
- 前後左右でズレる音の届き方
こうした要素を踏まえずに作られた音は、
いくら音源として完成度が高くても、現場では力を発揮しません。
私は制作段階から、
- 「このキメは、フォーメーションが完成した“その瞬間”に鳴るか」
- 「この静けさは、会場の残響で消えないか」
といった“現場基準”で音を設計します。
この視点は、実際に演舞を見てきた経験がなければ身につきません。
観客の反応を想定したブレイク・間
よさこいは、踊り手だけのものではありません。
観客のどよめき、拍手、歓声が加わった瞬間に、演舞は一段階上の次元に入ります。
そのためには、観客が反応する“余白”を音に組み込む必要があります。
- 一拍の“間”で視線を集める
- サビ前にあえて音を引く
- 掛け声が入るためのスペースを残す
これらは譜面上では説明しづらく、データ化もしにくい要素です。
しかし、実際の会場を知っている制作者なら、
- 「ここで声が上がる」
- 「ここで一瞬、空気が止まる」
という感覚が身体に染みついています。
AIは音の連続性を保つことはできますが、
人の反応を待つ“間”を設計することはできません。
この差が、会場全体の熱量に直結します。
映像・SNS時代の現場感覚
現代のよさこいは、会場だけで完結しません。
演舞は動画として切り取られ、SNSで拡散され、何度も再生されます。
つまり、
- どこが切り抜かれるか
- どの瞬間がサムネイルになるか
- 音と動きが一体となって“映える”か
こうした視点も、楽曲設計に含める必要があります。
私は、
- 「この8秒は、動画で何度も再生される」
- 「このキメは、スマホ越しでも伝わるか」
といった前提で音のピークを配置します。
これはAIが学習データからは掴みにくい、“今の現場感覚”です。
現場を知っている制作者の価値
総合演出設計とは、音楽だけの話ではありません。
踊り手の呼吸、フォーメーションの緊張感、観客の期待値、会場の空気──
それらを一つの立体として捉え、音に落とし込む作業です。
この仕事は、机上ではできません。
現場を見て、感じて、失敗も成功も経験してきた人間だからこそ可能になります。
AIがどれだけ進化しても、
「この会場、このチーム、この瞬間で、何が起きるか」を想像しながら音を設計することは、人にしかできません。
よさこい曲制作における人の価値は、まさにこの“現場を背負う感覚”にあるのです。
AI時代に選ばれる制作者とは──「作る人」から「共に考える人」へ
AIの進化によって、「音を作る」という行為そのものの価値は、確実に下がっていきます。
しかしそれは、制作者の価値が下がることを意味しません。
むしろ今、制作者の役割は大きく変わろうとしています。
AIを使うか否かではなく、どう向き合うか
AI時代において重要なのは、「AIを使うか、使わないか」という二択ではありません。
本質は、どこをAIに任せ、どこを人が引き受けるのかを自覚的に設計できているかです。
AIは、選択肢を増やすことができます。
スピードも、量も、網羅性も、人を圧倒します。
しかし、どの選択肢を選び、どれを捨てるのか──その判断には、必ず価値観が介在します。
よさこい曲制作において、その価値観とは、
- 「このチームは、今年、何を表現したいのか」
- 「勝ちたいのか、残したいのか、超えたいのか」
といった問いへの答えです。
この問いに向き合う姿勢こそが、AI時代における制作者の立ち位置を決めます。
制作者の役割の進化
かつての制作者は、「良い曲を作る人」でした。
しかし今、その役割は
「問いを立て、方向性を一緒に決める人」へと進化しています。
- 技術を提示する人
- 正解を教える人
- 完成品を渡す人
から、
- 迷いを整理する人
- 選択肢の意味を言語化する人
- 決断の背中を押す人
へ。
AIが登場したことで、「作業としての制作」は機械に近づきました。
だからこそ、人は“思考と感情の伴走者”としての価値を担うようになったのです。
依頼者と並走する存在としての価値
よさこいの楽曲制作は、依頼者にとって常に「決断の連続」です。
テーマ、方向性、強さ、静けさ、攻めるか守るか──
その一つひとつに、チームの覚悟が問われます。
そのとき、
- 「これが正解です」と言い切る制作者よりも、
- 「一緒に考えましょう」と言える制作者
が、今は求められています。
並走するとは、迎合することではありません。
相手の迷いを受け止めた上で、
- 「この選択には、こういう意味があります」
- 「この音を選ぶと、こういう未来があります」
と提示することです。
この対話の積み重ねが、最終的な納得につながります。
人が介在するからこそ生まれる“納得の一曲”
AIは、完成度の高い音を出すことができます。
しかし、「これで行こう」と腹を括る瞬間を生むことはできません。
よさこいの現場で本当に強い曲とは、
チーム全員が
- 「この曲で踊りたい」
- 「この音に自分たちの想いが乗っている」
と感じられる一曲です。
その納得は、音そのものから生まれるのではなく、
対話の過程と、共有された時間の中から生まれます。
AI時代に選ばれる制作者とは、
技術を誇る人ではなく、
音を通じて“考える場”をつくれる人。
「作る人」から「共に考える人」へ。
この変化を引き受けたとき、
よさこい曲制作は、AI時代においても変わらず人の仕事であり続けます。
まとめ|AI時代でも、よさこい曲は「人の仕事」であり続ける
AIの進化によって、音楽制作のハードルは確実に下がりました。
作曲、アレンジ、音源生成──「音を作る」こと自体は、もはや特別な行為ではありません。
しかし、よさこい曲制作の本質は、そこにはありません。
よさこいの楽曲は、
- チームの歴史を背負い、
- 踊り手の感情を乗せ、
- 観客と空気を共有し、
- そして次の世代へと受け継がれていく“物語の器”です。
その中核にあるのは、
言葉にならない迷い、覚悟、願い、葛藤──人の感情そのものです。
AIは選択肢を広げてくれます。
スピードも、効率も、提案力も、人を助けてくれる存在です。
けれど、
- 「この曲で行こう」
- 「この音に、自分たちの想いがある」
と腹を括る瞬間を生み出せるのは、人との対話だけです。
AI時代において、制作者の価値は「作れるかどうか」ではなく、
一緒に考え、迷い、決断に寄り添えるかどうかに移りました。
私はこれまで550曲以上のよさこい楽曲を制作してきましたが、
最後に強さを持つ曲は、例外なく
- 「音が良いから」ではなく
- 「この曲で踊る理由を、チーム全員が共有できている」曲でした。
もし今、
- AIで作った音にどこか違和感がある
- チームの想いをどう音にすればいいかわからない
- 技術より“納得できる一曲”を求めている
そう感じているなら、そこが人の仕事の出番です。
よさこい曲は、共に考えるところから始まります。
音を作る前に、想いを整理するところから。
そのプロセスごと、私は伴走します。
お気軽にお問い合わせください|まずは「考えるところ」からご一緒しませんか
AIを使う・使わないは、問題ではありません。
大切なのは、「このチームで、なぜこの音なのか」を言葉にできること。
- まだテーマが固まっていない
- イメージはあるが言語化できない
- 技術論より、想いを汲み取ってほしい
そんな段階からでも大丈夫です。
まずは、今考えていることをそのまま聞かせてください。
👉 よさこい楽曲制作のご相談はこちら(全国対応・オンライン可)
※ヒアリング重視/修正無制限/後払い制で対応しています。
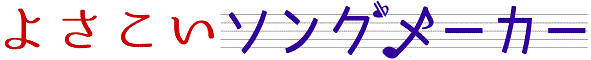


コメント